!記事内に広告が含まれています
「これって何か役に立つの?」
何かを調べているときや、本を読んでいるとき、ふとそんなことを考えたことありませんか?
以前の私は、すぐ使えそうな知識や即効性を重視しており「すぐに使えない情報=いらない情報」と考えていました。
けれど、年齢を重ねた現在、あることを実感しています。
“すぐに役立たない知識”ほど、あとからじわっと人生に効いてくるなぁ〜と。
今日は、そんな“遠回りの知”について書いてみました。

すぐに役立つことは、すぐに忘れられる

最近は、何でも「即効性」が求められていますよね。
便利なアプリ、タイパのいい動画、AIによる要約。
欲しい情報は瞬時に手に入り、使って終わり。──それはとても便利なことです。
でも一方で、「あれ、どこで調べたっけ?」とすぐに忘れてしまうことも増えていませんか?
実用性の高い情報って、言い換えれば「消耗品」という側面もある。
必要なときだけ取り出して、終わったらもう使わない。
そうした知識には、あまり“自分の血肉になる感覚”が残らないのかもしれません。
「役に立たない知識」は、いつか“人生の辞書”になる
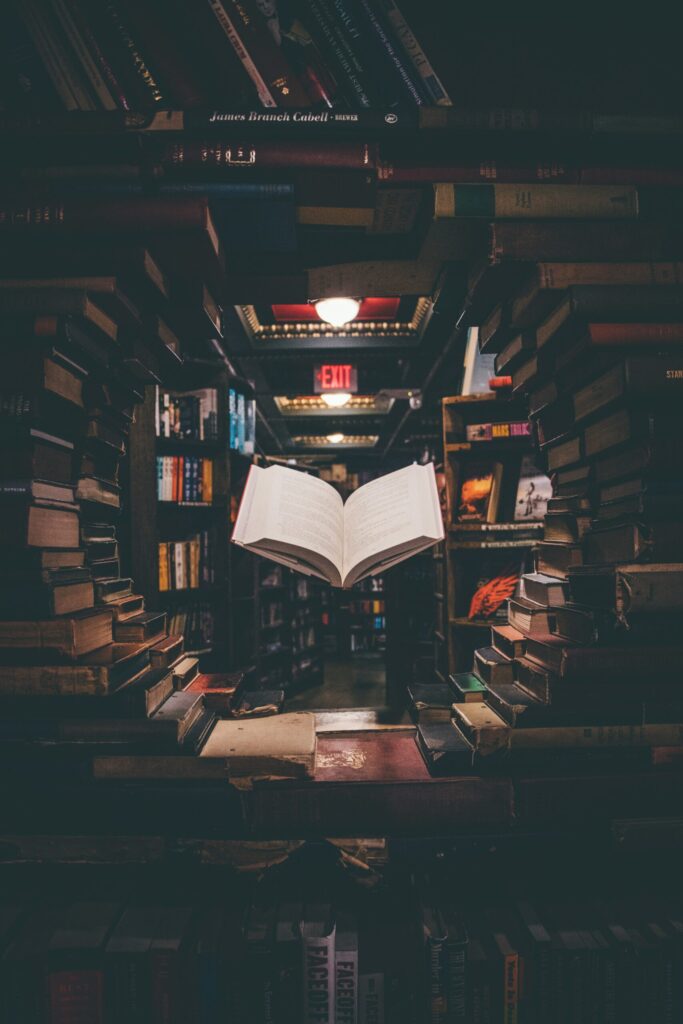
いつか読んだ哲学の本。
なんとなく観た静かな映画。
理解に時間のかかるアドラー心理学。
YouTube配信者「rの住人ピエロ」さんの動画チャンネル。
「よくわかんないな」「ちょっと変だな」「難しいな」と思っていたものが、ある日ふと、心の奥から浮かび上がってくることがあります。
落ち込んでいたある日、ふとアドラーのこんな言葉を思い出しました。
「他者の期待を満たすために生きてはならない。」
それだけで、肩の荷がすっと軽くなり、
何年も前に読んだ一文が、ようやく「自分の言葉」として腑に落ちた瞬間でした。
これは単なる例ですが、こういうことが他にもたくさんあります。
“あの時はピンとこなかった知識”が、あとから人生の辞書になっていたと気づくときが来るんです。
知識を“持っている人”ではなく、知識を“育てられる人”でいたい
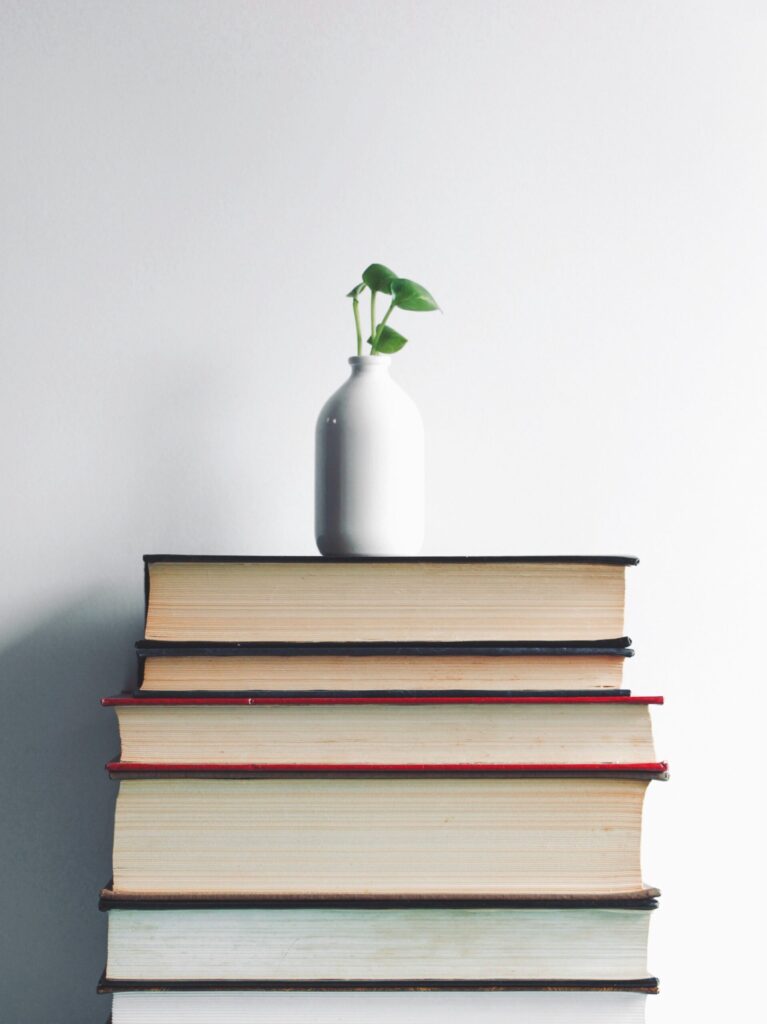
知識は、発酵食品のようなもの。
すぐに食べられないし、持っているだけでは腐ることもある。
でも、時間と経験が加わると、深い味わいになる。
あのとき見たこと、聞いたこと、読んだことが、人生の“調味料”になっていく。
だから、「これは今すぐ使えない。意味がない」などと切り捨てず、
“とりあえず知っておく”というゆるさが大切です。
それが、心の余裕にもつながるし、のちに感性の栄養になる。
遠回りが、いちばんの近道なのかもしれない

「無駄と思える知識もある日とつぜん思い出す」
これは私が、強く感じていること。
過去に見聞きした小さなエピソード、読んだ本の一節、誰かの言葉。
そのどれもが、思いがけないところで私を支えてくれています。
もしあなたが今、「これは何の意味があるんだろう?」と思っていることがあるなら、
そのままでいいんですよ。無理に意味づけしなくても、ちゃんと残ってくれます。
意味なんて、あとから勝手についてくる。
そしてそれは、必要なときにそっと背中を押してくれる。
📚ちょっとだけ紹介:私の「後から効いてきた」一冊
最後に、個人的におすすめしたい1冊をご紹介しておきます。
「難しそう」と敬遠されがちですが、じわじわ効いてくる劇薬的名著です。
🔗『嫌われる勇気』(岸見一郎・古賀史健 著)
アドラー心理学をベースにした対話形式の一冊。
実生活での実践は難しいよ!と、読んだ直後は感じるかもしれません。
しかし数年後、いろいろな経験を経て確実に効いてきます。
“自分のため”に書いてくれたようにさえ感じる名著です。
ぜひ「今すぐわからなくてもOK」な気持ちで手に取ってみてください。
まとめ
「すぐ役に立つ情報」にあふれた今の時代だからこそ、
“役に立たなそうなもの”を、あえて受け入れてみることで、人生は豊かになっていくと感じます。
役立たないように思えて、じわっと効いてくること。
そんな積み重ねで、人生や人格に深みが出てくるんじゃないかな。
そんじゃまたね〜
